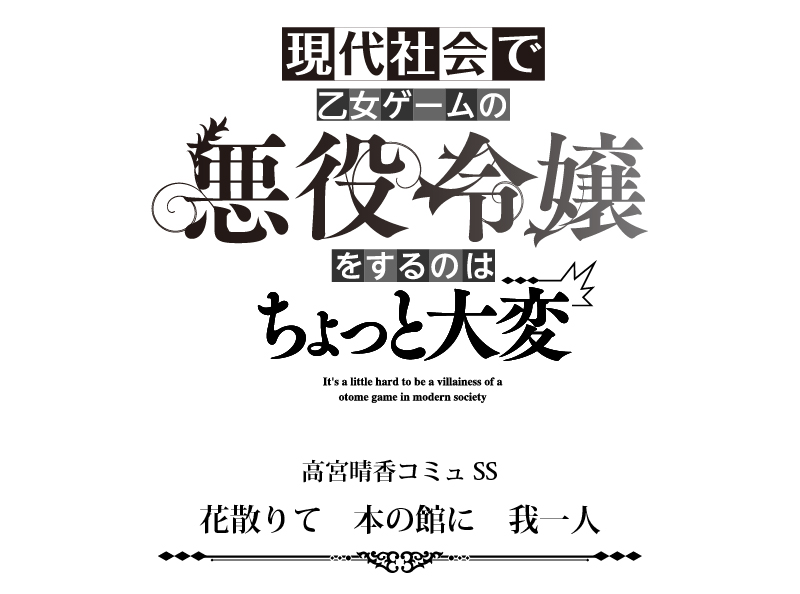私が生まれたのは、時代の移り変わりのはざま。
物心ついた時には戦争の空気が漂っており、国家総動員の名の下に何もかもが動員されていったあの時代は、華族もそこから逃れる事はできなかった。
そして、第二次世界大戦が終わり、私たち華族はその変化に翻弄される。
連合国による政治介入によってこの国は著しい変化を受け入れざるを得なくなったからだ。
私の青春は、そんな時代の奔流と共にあったのだ。
『もはや戦後ではない』
そんな時代の物語。
太宰治が心中をしたと知った時、
「ああ。もうあの人の本は読めないのか」
と嘆いた事を覚えている。
そんな私が大学に行けたのは、箔のためだった。
時代は高度成長期。
『太陽族』なんてのが街を闊歩していた時代。
私が在籍していた文学部も、そんな空気を多分に受けていた。
女流作家というのも本格的に出てきたこの時、私は次々と紡がれた物語の虜になった。
この頃の物語には、作者の思いが、叫びが、人生が文字越しに綴られていた。
私は初めて、己が箱庭の小鳥である事を思い知ったのである。
「ねぇ。高宮さん。短い夏を楽しみましょうよ」
そんな言葉を残した友人も卒業と同時に財閥一族に嫁いでいった。
私たちに流れる青い血は、高度成長と共に発展する財閥や新興企業に新たなる箔として認知されたのだ。
インドシナの戦乱が激しさを増し、米国だけでなくこの国をも巻き込もうとしていたあの時代。
そんな私にもお見合いの話が来る。
尾崎紅葉の『金色夜叉』みたいと思ったが、私には貫一はおらず、血以外に誇るものがない高宮伯爵家としては、このお見合いを断る選択肢はなかった。
私が嫁いだ家は、地方の新興財閥だった。
丁寧に迎え入れられたが、夫との生活で子供ができなかったのが不幸と言えば不幸なのだろう。
夫に妾が居て、そっちが子供を産んだのも夫婦仲を冷やすに十分だった。
夫の妾が谷崎潤一郎の『痴人の愛』のナオミみたいと思ったのは、あの時の私の負け惜しみだった。
文学少女から妻になりきれなかった私と、ナオミみたいな女に惚れこんだ夫の当然の破局。
離婚が家の恥と言われる空気がまだ残っていた上に、血以外に価値がない高宮伯爵家にとって私が家に帰されるという事は、夫の実家からの支援がなくなる事を意味する。
高宮伯爵家の没落は必然だったのだろう。
父は私を怒り、嘆き、酒に溺れて死に。
母は家財を売り払いながら、華族の見栄をなんとか守りつつもその人生を終えた。
私の手元には本しか残らなかった。
菊池寛の『真珠婦人』のように生きるには純粋過ぎ、川端康成の『伊豆の踊子』のように生きるには世間を知り過ぎていた。
だからこそ、一人になった私は働かざるを得ない所に追い詰められたのだ。
「学内のマドンナで才女だった君の頼みだ。同期のよしみで席を用意しておこうじゃないか」
三島由紀夫が割腹自殺をし、志賀直哉や川端康成も世を去ったあの頃。
まだ、文壇に上流階級のサロンの残り香があった時期であり、私はそんな伝手を使って出版社に就職する。
この仕事は私にとって天職だった。
社会が、女性進出の波が決定的となったこの時代、私は時代の波に乗った。
女性の社会進出の旗手の一人として、就職した出版社から持ち上げられたのだ。
華族の子女ですら働く。
この国が望んだ姿を私は演じ続けた。
「帝都学習館学園の司書ですか?」
ベトナム戦争が西側の敗北で終わろうとしていたあたりで、私は帝都学習館学園の司書にスカウトされた。
資格は持っていたが、その唐突さに疑念がわかなかったと言えば嘘になる。
文壇の周囲には政治家やパトロンたちが居たし、新聞が情報を発信していた時代の名残として記者と親しかった事もあり、彼らの忠告から私の役割が終わった事を悟った。
「君を第二の与謝野晶子にしたくない人たちがいたという事さ」
冷戦は未だ続き、それでも我々は豊かに、退廃的になってゆく。
時代は司馬遼太郎から村上龍を経て赤川次郎へ。
そして、帝都学習館学園の中央図書館という終の棲家を手に入れたのだ。
時代から意図して取り残され、図書館という終の棲家で本を相手にする穏やかな日々。
ただ、長く務めると必然的に慕う生徒も増えてくるし、彼らが大人となり教師や司書としてこの学園に戻ってくることもあった。
そんな時、大人として年長者として振舞った結果、いつのまにか先生と呼ばれるようになった。
私には島崎藤村や夏目漱石みたいに、人を導く才能はない。
私は宮本百合子みたいに社会に問いかける事もしなかった。
ただ、本と共に、本だけを持って歩み続けた人生。
いつの間にかついたあだ名は『図書館の魔女』。
魔女狩りに遭わずにすんだものだと知った時の苦笑は今も覚えている。
帝都学習館学園中央図書館館長就任。
それは、私高宮晴香の人生の集大成と言ってもいいだろう。
人が持つ感情というものは唐突で理解しがたいものがある。
それが耳に届いた時、私の中で何かが動いたのだ。
「いいわよ。そんな事もあって、なんだか私の生は宙に浮いている感じがするのよ。もし私が杜子春と同じ場所に立った時、私は声をだすことができるのか? 正直、わからないのよ」
私のいた場所からは、彼女の声しか聞こえない。
風が舞って、花吹雪が私の視野を奪う。
「桂華院は桂華院だよ。俺の知る桂華院ならば、きっと声をあげるさ。『仙人なんてつまらない』と言ってな」
「ぷっ。なにそれ?」
話していた二人が去った後でも、桂華院という名前が耳に残り続けた。
今だからこそ思う。
あの時から、私は先生をしようと思ったのだ。
仙人になるかもしれないと言った彼女を、ちゃんと人として導くために。
「おはようございます! 高宮先生!」
「おはようございます」
(ぺこり)
そんな春先のある日。
ランドセル姿のまぶしい三人娘とすれ違う。
「おはよう。春日乃さん。桂華院さん。開法院さん」
私の挨拶に会釈して彼女たちは学び舎に駆けてゆく。
その姿が懐かしくて、まぶしい。
「花散りて 本の館に 我一人 か……」
久しぶりに俳句を詠んだ。
その歌も春風と共に空に消えてゆくのを見届けて、私は一人私の城へ帰る。
【用語解説】
・もはや戦後ではない……1956年経済白書より。
・太陽族……石原慎太郎『太陽の季節』に憧れた青年たちの総称。